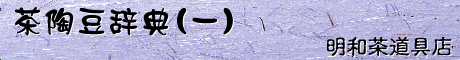

高麗茶碗の堅手(かたて)・粉引(こひき)・熊川(こもがえ)などで長年使っている間に、内外に生じた紫鼠色のしみを、雨漏りのしみにみたてて、雨漏と称しています。

伊賀焼きは伊賀(三重県阿山郡)の産なのでこの名前があります。近接の信楽とは国こそ違え同系で、桃山以前の作はほとんど見分けが付かないくらいです。伊賀の窯には槙山(まきやま)と丸柱(まるばしら)がありますが、ことに槙山は国境の三郷山の土を使っていて信楽と同じ土なので、中世の作では古信楽とほぼ同じです。
伊賀焼きが特色を出したのは茶道の盛んになった桃山時代からで、織部好みの形の奇抜な手強い作の花入や水指が焼かれ、これを古伊賀といいます。この場合の古伊賀というのも、古備前同様時代の新古とは無関係で、茶道具として伊賀では最上の意としていわれたもののようです。
井戸は古来高麗茶碗の王といわれ格別貴ばれていますが、俗に一井戸二楽三唐津というように、茶碗を通じての最上とされ、その名は講談や落語にまで取り上げられて、茶碗といえば井戸の名を連想するほどに有名になっています。
こういう井戸の評判というものは、その姿が堂々としていて、作行きが優れ、枇杷色の釉も美しく、また竹の節高台やカイラギなど茶碗としての見所を兼ね備えている点にもよりますが、天目や砧青磁茶碗に飽いた室町の堺の茶人たちが、自由ではつらつとした動きのある、初めて接した高麗茶碗である井戸であったという歴史的な理由によるものと思われます。
井戸の名については、見込みが深いからつけられたという説もありますが、これは奈良興福寺の寺臣、井戸氏所持の茶碗が当時名高く、これから起こったものという説が一般的です。
ちなみに井戸の名の起こりであるこの茶碗は、のちに筒井順慶に伝わって、深めで高台が高いので筒井の筒茶碗といわれ、略して筒井筒と呼ばれ、井戸の中の名碗となっております。
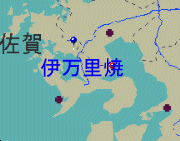
日本で最初に磁器が焼けたのは元和元年、肥前の有田(佐賀県)で、朝鮮役後帰化した陶工李三平が有田泉山に良い原料を発見してからである。元和・寛永頃の初期の染め付けを、近年は初期伊万里と呼んで、いわゆる古伊万里と区別していますが、この時代にも水指や花入などの茶道具がすでに焼かれています。
有田焼は伊万里焼きともいわれ、世上にはこのほうが良く通っていますが、これは有田焼が伊万里港から船積みされて諸国に出されたので、他国の人々にはかえってこの名の方で知られていたからです。白磁や染め付けはたちまちにして肥前窯業の主流になって、従来の唐津焼きの陶器に取って代わりましたが、肥前一帯の磁器を総称して有田焼または伊万里焼と呼ばれています。ちなみに柿右衛門焼や鍋島焼も広義の伊万里焼の中に含まれています。
織部焼きというのを広く共通の織部好みの作風からとらえて、瀬戸織部・唐津織部といっているように、窯別を超えて広義に解することもできるが、普通は美濃瀬戸における織部焼きを指して呼んでいます。
九尻窯の加藤四郎右衛門景延が慶長初年に九州唐津の進歩した登り窯(多室)を取り入れて、美濃に初めて新式の窯を築きましたが(これがいわゆる元屋敷窯です。)、古式の穴窯(単室)に比べて、この有利な登り窯はその後たちまちにして美濃一帯に普及しました。織部焼きはこの新しい窯になってから生まれたものです。
織部焼きは美濃瀬戸の中でも最も作風の華やかな、いかにも桃山の好みをそのまま表したような陶器です。形の上でも、茶碗はすべてデフォルメされた沓形となり、ことに鉢や向付ではとりどりの意匠に変化をつくしています。
織部焼きもその手法の上からいろいろに呼ばれますが、ふつう織部といわれている、緑のいわゆる織部釉のかかった最もポピュラーな手は、青織部といわれます。


唐津焼は、肥前一帯(佐賀県と長崎県一部)の広い地域に散在する300近い窯で焼かれた陶器の総称です。それが唐津の名で呼ばれたのは、その製品が唐津の港から各地へ出されたのが元であろうといわれています。
唐津焼が盛んになったのは桃山時代になってからで、秀吉の文禄・慶長の役で多数の朝鮮陶工が鍋島藩の手で連れて来られたが、彼らは領内の肥前一帯で窯を築き、故国の李朝陶器にならったものを焼き初めてからです。慶長から元和にかけてが唐津焼の全盛時代で、ここに当時の日本ではまだ極めて珍しい、釉のかかった、また錆絵のある陶器が、北九州の肥前地方で大量に焼造されるようになったのです。やがて元和元年には朝鮮陶工の李三平が有田の泉山に磁器の原料を発見して白磁を焼いてから、有田を中心に主な窯は競って白磁や染付の焼造に転向したので、唐津焼は次第に衰微して肥前窯業の主流ではなくなっていきましたが、一部では余命をとどめて幕末まで続きました。それで全盛期の唐津焼を特に古唐津といって、その後の唐津焼と区別しています。
斑唐津も唐津の大きな特色の一つですが、これには二手があります。従来茶人に斑唐津と呼ばれているのは、沓茶碗やウロコ(三角)口割高台の沓鉢で、飴釉と白ナマコの美しく片身替わりに掛分けたもので、素地は粗く柔らかく、沓鉢の胴にはヘラ彫りがあり、高台内に王子の印があります。一種の形物とみられていますが、数の少ないもので古来茶人に珍重されています。王子印の手は、あるいは萩かとも近年言われています。
いま一つは近年唐津研究家の間で斑唐津と命名されたもので、これは白ナマコだけで、岸岳の帆柱・皿谷・山瀬などのものです。この手は雑器の生まれで、茶碗やぐい呑みに見立てられています。ことに帆柱のぐい呑みは有名です。帆柱の素地は粗い砂土で堅くて特色があります。
明治の初め頃、屋島焼きの陶工祖春が小豆島に来島し、茶人秋光と共に神懸山(寒霞渓)の麓に陶窯を築き神懸(かんかけ)焼きの初代として、茶陶器の製造を初めました。
その後、加賀の国九谷より陶工香悦が来島し、香悦独自の釉薬をもって楽焼き特有の軟さ、深い味わいを持たせながら、実質的には本焼きに近い堅牢さ優美さを有する、一種独自の焼成方法をもって現在の神懸焼き独自の製品を造っています。

黄瀬戸釉は瀬戸焼きの大きな特色の一つです。その起こりは鎌倉時代の古瀬戸に見られる黄緑色の灰釉に始まり、その釉調は室町時代になってようやく安定するようになり、黄瀬戸としての特色を示すようになりました。黄瀬戸は瀬戸焼きを通じての伝統的なものになりました。
桃山時代の黄瀬戸は、一般的にグイノミ手・アヤメ手・菊皿手などに分けられています。
グイノミ手とは、懐石に使われる酒杯のぐい呑みに多いので、この様に呼ばれるようになりました。厚出で釉肌には光沢があり、釉調もやわらかい感じです。一部に白いナマコ(卯の斑)の出た場合が多いようです。多治見北方の山間の大萱(おおかや)などで作られました。
アヤメ手とは、この手の代表作に菖蒲の彫り文様のある有名な銅羅鉢があるので、こう呼ばれています。釉肌が油揚げに良く似ているので油揚(あぶらげ)手とも呼ばれています。グイノミ手より薄手で見込みや外側にヘラ彫りや押し型で簡素な文様があり、丹礬(たんぱん)の銅緑や鬼板(酸化鉄)の褐色を点じて彩りにしています。釉肌はやわらかくて光沢のないのが上手(じょうて)である。大萱ではこの手の名品が作られていたようです
菊皿手とは、グイノミ手やアヤメ手より少し時代が下がるもので、作風も下手(げて)になり雑器が多いようです。大平(大萱の隣)や笠原(多治見の南)で大量に焼かれた菊形の小皿がこの手なので、こう呼ばれるようになりました。厚手で釉は光沢が強く、鮮やかな黄色で、細かい貫入があります。縁には銅緑釉がかかり、これが流れて黄・緑が入り交じって派手な感じがします。

楽焼きを除いた近世以降の京都のやきものを京焼きと言います。その起こりは、寛永元年に瀬戸より、陶工三文字屋九右衛門が京都の粟田口三条通りに来て開窯したのが始まりと言われています。
その起こりは、粟田口三条の問屋で瀬戸・信楽から茶陶を取り寄せていたものを、茶の湯が隆盛になるにつれその需要が増えたので、現地から陶工を招いて窯を開かせたのではないかと言われています。これに伴って瀬戸や信楽の技法も取り入れられ、粟田口焼の土台になったと思われます。
京焼きは、元禄時代までは粟田口を主流として、ついで清水(きよみず)・音羽(おとわ)・御菩薩池(みぞろいけ)・清閑寺(せいかんじ)などが興りました。初期のものはほとんど無印ですが、その後音羽・御菩薩池・清閑寺などは印を押すようになりました。
洛北仁和寺門前の御室(おむろ)焼きは、京焼きの一つではありますが、仁清による作品は別格に扱われています。仁清(没年元禄元年)は、丹波野々村出身の丹波焼きの陶工で野々村清右衛門といい、京都の粟田口や瀬戸で修行をして技法を習得し、後に金森宗和や仁和寺宮覚深法親王・堂上貴顕などに引き立てられ御室に窯を開きました。仁和寺宮から仁和寺の「仁」と清右衛門の「清」から「仁清」の号を賜り、世に仁清と言われています。
京焼きでは従来もっぱら陶器だけを焼いていましたが(僅少の例外はあります)、江戸時代中頃になると時代の変化に促されて、磁器の染付や赤絵を焼くようになりました。これが清水で始まり、五条坂を中心に清水焼といわれ京焼きの主流になりました。

九州の有田に生まれた磁器の染付や赤絵は、遠く離れた北陸の加賀にも影響して、いわゆる古九谷が起こっています。古九谷は加賀大聖寺の初代藩主前田利治が、家臣の後藤才次郎に命じて明暦年間に、大聖寺川の上流に沿った奥深い山間の僻村九谷で開かせたもので、元禄初年まで続いたといわれています。幕末に起こった再興九谷と区別して、古九谷と呼ばれています。
色絵は古九谷の大きな特徴で、色釉が濃厚鮮美で意匠に優れ、強烈な賦彩がやや濁った光沢のない素地と良く調和して、日本の色絵磁器としては最高の芸術性を示しています。また色絵の一種に、素地を青・緑・紫・黄の色釉で塗りつぶした手があり、赤がないので俗に青手(塗り潰し手)と呼ばれているものがあり、意匠の優れたものが多くあります。
染付を藍九谷といいますが、近年同じ手のものが有田の稗古場(ひえこば)などで大量に発掘されたので、藍九谷の大半は初期伊万里ではないかともいわれております。同じように色絵古九谷も、あるいは一部に伊万里焼きが交じっているのではないかとの見方もあります。
古九谷は元禄以後一時絶えたといわれていますが、文政7年(1824)になって大聖寺の豪商吉田屋(豊田伝右衛門)がその再興を図り、九谷に窯を築きました。古九谷の青手風のものを焼いたので、青九谷または吉田屋と呼ばれています。翌8年には便利な山代温泉の越中谷に窯を移し、天保年間には経営者が変わって宮本屋窯となり、飯田八郎右衛門の絵付けした緻密な赤絵金襴手のいわゆる八郎手を特色とするようになりました。この山代窯には慶応2年(1866)に京都から永楽和全が指導に招かれ、この時代のものを九谷永楽といいます。和全の山代滞在はわずか5年ではありましたが、これにより九谷焼は金襴手などの技法の上で飛躍的に進歩しました。
瀬戸窯以外の日本各地で焼いた陶磁器をいいます。
建窯でできた茶碗を建盞(けんさん)といいますが、天目を代表するもので、一番有名です。建窯というのは福建省の水吉県にあり、もと建甌県、ついで建陽県に属していたので、建窯と呼んでいます。
日本の鎌倉時代に当たる南宋から元代にかけてが最も盛んに焼かれた時代で、製品は天目(茶碗)が大部分を占めていたようです。唐代に盛んだった団茶がすたれ、宋代になると新たに抹茶が流行するようになりましたが、このために従来の青磁茶碗に代わって抹茶向きに工夫された天目が建窯で生まれ、世の需要に応じて大量に生産されるようになりました。
建盞はまずその形に特色があり、ついで窯の中の偶然の変化、つまり窯変(ようへん)で釉面に種々の美しい自然の文様が現れることがあり、茶人はこれを曜変(ようへん)・油滴(ゆてき)・禾目(のぎめ)などと呼んで特に賞味しています。
仁清の弟子に有名な尾形乾山(おがた けんざん 1743年没)がいます。乾山は画家光琳(こうりん)の弟で、京都の裕福な呉服商雁金屋(かりがねや)に生まれました。乾山はもと京都鳴滝(なるたき)の窯名ですが、のちに号としても使われました。乾山は年少の頃から読書や書道を好み、豊かな教養は青年時代に培われ、それらは後年の作品の上に大きな特色となって表れています。
父の没後若くして莫大な遺産を譲られた乾山は、御室仁和寺門前に習静堂と号する山荘を構えて悠々自適の生活を送るうち、近くに窯のあった仁清に師事して陶法を修得しました。窯を乾山と名付け、作品の銘としました。
正徳二年(1712)京都の二条通丁字屋町に移るまでの鳴滝時代の作を鳴滝乾山といい、この時代には兄光琳が画を書き、乾山が詩を賛した兄弟の合作もあります。丁字屋町時代の作を二条乾山と呼び、ついで享保の中頃には江戸に下って入谷(いりや)窯で焼いたので、江戸時代の作を入谷乾山といいます。江戸の晩年には画も描いており、画家としても有名です。元文二年(1737)の秋から冬にかけて、下野(しもつけ 栃木県)佐野でも陶器を焼きましたが、これを佐野乾山と言います。
古雲鶴も含めて、井戸・三島・熊川(こもがえ)・堅手(かたて)・斗々屋(ととや)・伊羅保・粉引などの朝鮮茶碗を昔から高麗茶碗と呼んでいます。高麗時代の茶碗という意味ではなく、朝鮮のお茶碗という意味でこう呼ばれています。室町時代末期から桃山時代頃には、朝鮮のことを高麗と呼んでいたためと思われます。
伊羅保(いらほ、いらぼ)という名は、地名からという説もありますが、確かな証拠もないようで、やはり通説のように、肌が「いらいら」と荒いところから出たもののようです。箱書きには、イラホ・出皰・意羅保・伊良保などと書かれています。
伊羅保はその作風から見て江戸初期にあたる時代に焼かれたもので、釜山に近い昌基(チャンギ)の窯で出来たことが発掘でわかっています。なお伊羅保に限って、茶人は少しの傷や繕いでも許さぬ慣わしになっています。
伊羅保は寂び物でも筆頭格で、茶の点てやすいお茶碗でもあります。
高麗茶碗の一つで、粉引(こひき)又は粉吹(こふき)といいます。白粉が全面にひいてあるのでこの名がつきました。素地(きじ)の全面に白泥で化粧がけをして、これに透明な釉をかけたもので、この手法は刷毛目・三島と共通するもので、その年代もほぼ同じ頃といわれています。
李朝初期から中期にかけて全羅南道でのみ焼かれていたと思われます。土に鉄分が多く黒いため白く化粧がけをして、その上に柔らかな透明釉をかけます。
釉膚は柔らかく、白い色調があたかも粉を引いたように見えます。古来粉引きの見所とされるのは、火間といわれる釉のかけ残しが胴にあることで、特に茶人に好まれています。
粉引には雨漏りのできたものが多く、景(けしき)としてよろこばれています。また茶碗の他に徳利が有名です。
御本とは御手本のことですが、御本茶碗というのは、日本から御手本(切型)を朝鮮に送って、釜山の倭館(わかん)窯やその付近の窯で焼かせたもので、つまりは注文品ということです。時代は慶長から享保までわたっています。
御本三島は、文様も本来の三島とはかなり趣を異にしていて、いかにも日本の陶工の手にでも成ったような感じで、対馬から渡って釜山の倭館窯で焼いた玄悦や茂三(もさん)などの手によるものだろうといわれています。


慶長3年(1598)島津義弘が朝鮮から連れ帰った陶工による開窯が起こりで、その中の金海(星山仲次)は同6年(1601)頃義弘の居館のある帖佐(ちょうさ)の宇都(うと)に呼ばれて御庭窯を開いたのが有名な古帖佐の始まりです。
義弘の没後、金海は鹿児島藩主家久に招かれて、堅野冷水(たてのひやみず)に御庭窯を築きました。以来幕末に至るまで薩摩焼きの中心となって発達しました。
慶安元年(1648)有村碗右衛門は藩主光久に請うて上洛し、仁清の御室窯で修行し、錦手を学んで帰国後、堅野でも薩摩錦手が始まりました。後には錦手が薩摩焼きを代表するほど有名になりました。京焼きに似ていながら又別の趣があり、茶の湯の世界でも人気があります。薩摩の錦手は素地が白く、釉はやや黄ばんでいます。
薩摩に来た朝鮮陶工の朴平意らが、慶長8年(1603)に苗代川(なえしろがわ)に開窯したのが苗代川焼です。苗代川焼は日用品の黒物を特色として今日なお隆盛で、民芸愛好家に好まれています。黒物では苗代川焼と並んで竜門司(りゅうもんじ)焼も有名です。
薩摩焼きでは黒物のいわゆる黒薩摩は日用品の下手物(げてもの)、白薩摩は上手物となっています。

信楽焼は滋賀県甲賀郡の信楽地方で鎌倉時代から焼かれています。今日もなを長野・勅旨(ちょうし)・黄瀬(きのせ)・神山(こうやま)などの窯で焼かれています。瀬戸や備前と並んで、現存する日本最古の窯の一つです。備前と同様素焼きの焼き締めを特色とする日本固有の陶器です。
中世の窯は瀬戸や備前と同じ穴窯でした。この時代には備前などの中世古窯と同様、壺やすり鉢などの日用雑器を造っていましたが、室町時代になると茶の湯が隆盛になり茶道具の需要が増し、信楽でも茶壺が盛んに焼かれるようになりました。
現代の信楽の作家では、高橋楽斎や上田直方が有名です。

志野焼の由来は、古来の伝説によれば、室町時代末頃の茶人志野宗信の好みで焼かれたのでこの名が付いたと言われていますが、また近年の説によると、元禄頃大阪の茶人城宗信がこの手の茶入れに「篠」と銘々したのがもとで、この名が起こったともいわれています。なお志野焼の創始については、天正年間美濃久尻窯の加藤四郎右衛門景延が焼いたのが起こりで、景延は白薬手の茶碗を朝廷に献上して、これを筑後の朝日焼きと命名されたと伝えられています。
美濃瀬戸の素地は鉄分の少ない白めの土ですが、志野の素地は特に美しく、俗にモグサ土といわれる白土で、厚手に作られ、これに淡雪のような、白い半透明の長石釉が厚めにかかっています。そして肌には針で突いたようなす穴のあるのが、古志野の約束です。釉の薄い口縁や、絵の部分や、釉際には、火(緋)色と呼ばれる美しい赤みがほんのり出て、志野の優れた景色になっています。
白い志野釉の出現も、日本の焼き物の歴史の上では画期的な出来事でしたが、それにもまして特筆すべきことは、従来焼き物の文様といえば、ヘラ彫りか押し型の手法しかなかったところへ、志野焼では新たに釉の下に鬼板(酸化鉄)で絵付けするという、かつて見ない文様装飾の新手法が編み出されたことで、おそらく中国の染付に影響されて、長石釉を発明し、付近でとれる鬼板を呉須代わりに使って絵付けする事を思いついたものと想像されます。また志野茶碗の形も、初期のものは瀬戸黒ふうですが、次第にいわゆる沓形の、デフォルメされた新デザインが生まれています。これは御所丸の形とも共通するものですが、当時の茶の湯の世界の優れたリーダーであった織部の創意であったと思われます。志野も元禄頃までは織部焼きと呼ばれていましたが、後に志野の名が生まれてからは織部焼と区別されるようになりました。
◆ 無地志野・絵志野
志野釉だけで文様のないのは無地志野といい、釉の下に鬼板で絵付けしたのは絵志野といいます。釉が不透明で厚いので絵は自然と簡素で太くなり、それが濃淡見え隠れに現れて、絵志野特有の味わいがあります。
◆ 鼠志野
志野の一種で鼠志野というのは、白い素地に褐色の鬼板の泥を化粧がけし、これに文様をヘラ彫りして白く表し、志野釉をかけたもので、一見白象嵌のように見えます。地の部分が鼠がかって見えるので、こう呼ばれています。
◆ 赤志野・紅志野
鼠志野と同じ手法で赤く焼き上がったものを、赤志野といっています。ただし紅志野は、鬼板の代わりに赤ラク(黄土)で化粧したもので、赤の発色は赤志野よりも淡い色をしています。赤ラクの上に鬼板で絵付けしているものもあります。また素地が白土と赤土の練り上げ手になっているのもあって、これを練り上げ手志野といいます。
茶人が古来茶陶の染付の最上としているものに、祥瑞(しょんずい)があります。作品はすべて茶道具あるいは懐石道具に限られており、もっぱら茶事用として造られたものと思われます。とくに沓茶碗とか、蜜柑水指とか、中国本来の器には見られぬ、日本の茶人の好みによって景徳鎮の民窯に造らせた注文品であることが推測されます。しかもその遺品が日本だけにしかなく、中国にも西洋にもないということがその証であるとされています。
祥瑞と呼ばれるのは、時に「五良大甫呉祥瑞造」の染付名があるので、茶人達がそれにちなんでこの類の通称としていい慣わしたものです。昔の茶人はこの「五良大甫」を五郎太夫と解釈して、伊勢松阪の伊藤五郎太夫が渡明して景徳鎮で焼いたもので、「呉祥瑞」はその地での五郎太夫の号であったという説を後世に伝えました。この説は今なお尾を引いていますが、実は「五良大甫」とは五男という意味の中国の俗称で、要するに景徳鎮の陶家には多い呉姓の一人である呉祥瑞の作というのが本当のところのようです。
また以前は南京赤絵の中に入っていたもので、近年は色絵(赤絵)祥瑞と呼ばれているものもあります。
青磁も天目と並んで室町時代から貴ばれた唐物の茶陶で、桃山・江戸時代を通じて今日においてもその伝統は依然として変わりません。鑑賞界における青磁の研究の進歩とともに、その評価は今日いよいよ高まりつつあります。
我が国は世界でも屈指の青磁の名品の多い国として国際的に注目されていますが、それはひとえに審美眼の優れた昔の茶人達が、早くから青磁を賞美して大切に保存に努めてきたおかげと言えるでしょう。欧米では青磁の鑑賞は近代に入ってからの現象ですが、日本では本場の中国に次いで早い方で、「ひそく(秘色)」といわれた越州窯青磁は、すでに藤原時代に貴族の間で賞美され、茶陶の官窯青磁や砧(きぬた)青磁は鎌倉時代には我が国に渡って来ています。

膳所(ぜぜ 滋賀県大津市)は、朝日(山城)・志戸呂(しどろ 遠江)・古曽部(こそべ 摂津)・赤膚(あかはだ 大和)・高取(筑前)・上野(あがの 豊前)と共に、遠州好み七窯として有名です。
膳所の窯は元和ごろからすでにあったもので、当時の城主菅沼織部は光悦・松花堂・遠州とも親しかった優れた茶人でしたので、この時代から茶陶は焼かれていたとみて良いでしょう。次の城主は遠州の弟子の石川忠総です。
膳所の古窯は大江と国分にあり、遠州好み膳所茶入の名物大江(根津美術館蔵)は前者の生まれです。大江も国分も主に茶道具を焼やいていますが、大江の方は素地が白めで、また釉は両者とも瀬戸系の錆釉ながら雅味があり、時に黄飴釉の隠見するのも約束です。

瀬戸は備前(びぜん)・信楽(しがらき)・常滑(とこなめ)などと並んで、現存する日本の陶窯の中では最古のものであります。しかし他の備前・信楽・常滑などが、農民用のカメや壺などの雑器を作っていたのに対し、瀬戸では中国の青磁・天目をまねた灰釉(黄瀬戸釉)や黒飴釉(天目釉)をかけた上手(じょうて)物を、すでに鎌倉時代から作っていました。
瀬戸はこのような先進技術をもっていたので、室町時代の中期以降、茶の湯が普及するにつれ唐物だけでは間に合わなくなり、当然瀬戸で茶入れなどが作られるようになったと思われます。この瀬戸の先進技術は、他の国焼窯にも影響を与えています。この様な所から瀬戸は、他の日本古来の国焼きとは別格に扱われていたようです。瀬戸が昔から中央の貴族層と密接に結びついていた事にも、関係があるかもしれません。
文化年中、杉山吉右衛門が琵琶湖湖西の地に多くの陶工を集め、上品な磁質のやきものを焼いたことに始まる。
後を引き継いだ中江与兵衛は、幕末の名工の一人、仁阿弥道八の門人といわれ、精巧な茶器を中心に雅味豊かな作風で盛況を見るが、後に廃窯となる。
染付は明代以後の中国の焼き物を代表するもので、茶陶に取り上げられているのが多いものです。
染付というのは、白磁の釉下に呉須(ごす 天然コバルト)で青色の文様を描いたもので、中国では青花と呼ばれています。この「染付」とはもとわが国で藍染めの麻布を指した言葉で、白地に藍文様が似ているので転用されたようです。
なおちなみに、呉須の名の起こりは、浙江省の紹興付近から良質なものが出ましたが、この地方は古くは呉の国と呼ばれていましたので、わが国ではこれを呉州産という意味で呉州(ごす)と呼び、また呉須とも書くようになったと思われます。

天目の中で建盞(けんさん)と並んで室町時代から賞美されているものに玳玻盞(たいひさん)があります。この名は釉調が鼈甲に似ているので付いたものです。一名鼈盞(べっさん)とも言われています。中国江西省吉安県の永和鎮の吉州窯で南宋から元の時代にかけて盛んに量産されたもので、吉安天目または吉州天目ともいわれています。
玳玻盞の特色であります鼈甲釉は、黒飴釉をかけた上に、ワラ白釉(失透性のワラ灰釉)を斑にふりかけたもので、さながら鼈甲のような釉調をして大変美しいものです。また両釉の二重がけで種々の文様をあらわしているものも、玳玻盞独特の他には見られぬ意匠です。
この地方で行われた剪紙細工(きりがみざいく)−紙を種々の文様の型に切り抜いた切り紙−を陶器の文様装飾に応用したものです。この切り紙には、梅花・唐花・鸞(らん 尾長鳥)・竜・吉祥文字(富貴長命・金玉満堂・福寿康寧等)などがあり、これを見込みの黒釉地の上に貼り付けて、その上からワラ白釉をかけ焼き上げると黄飴地に黒文様の玳玻盞独特の剪紙紋が生じます。その文様によって、梅花天目・鸞天目・竜天目・文字天目などと呼ばれています。
玳玻盞の名物になっている木の葉天目は、黒釉地に実物の木の葉を貼り付けて焼いたものです。
室町の茶の湯では、茶入れといえば唐物、茶碗といえば天目でした。その古い伝統から天目は後の世にも特に貴ばれ、格別の扱いを受けて、神仏前の献茶や貴人点に使われています。
天目という名は中国の名称ではなく、日本で付けた名で、その起こりは浙江省の天目山から出ています。この地方は古来茶の名産地として知られたところで、抹茶の流行した宋代には、抹茶用の茶碗として新たに生まれた建窯で作られたものが従来の青磁に代わって使われるようになり、天目山の禅僧達の間でも盛んに使われていたようです。
この天目山には有名な禅宗の寺々があり、鎌倉時代には日本からこの地に留学する僧も少なくありませんでした。この留学僧達が帰国の際に建窯の茶碗を持ち帰り、やがてこれを天目山にちなんで日本では天目と呼ぶようになったと言われています。
天目の名は初めは建窯の茶碗、すなわち建盞(けんさん)だけに限られていましたが、のちには玳玻盞(たいひさん)はじめ他窯の茶碗にも使われるようになり、ほとんど茶碗の別称のようになりました。

仁清の作はもっぱら茶道具や懐石道具で、素地は黒谷の白い上土を使い、釉にも主に茶入に用いた瀬戸風の錆釉もあれば、色絵の際の仁清独特といわれる、半透明のやわらかい白釉(俗に仁清釉という)もあります。信楽風の素焼きのいわゆる仁清信楽も特色の一つですが、唐津風のものもあり、また御本や高麗茶碗を写した作もあります。絵付けには錆絵や呉須絵があります。
しかし仁清の名を最も高めているのは優美な色絵(錦手)で、これを宮方茶人の庇護のもとでよく大成したのは仁清の功績で、京焼きの大きな特色である錦手を確立した意味から、彼を京焼色絵の祖と言っても過言ではありません。
仁清の絵付けの描法は狩野あるいは土佐風で、手法には蒔絵の影響も見られ、器形や文様も多くは堂上好みで、その作風には日本趣味の特色が著しい。これは仁清の茶器を愛好したのが、主に宮方や堂上貴顕であったからだろうと思われます。
さらに仁清の最大の特色、その本領とも言うべきは、ロクロによる陶技の絶妙なことで、その精巧な薄手の優美な作ぶりは、まことに古今まれなロクロの天才といって良いでしょう。
禾目(のぎめ)天目というのも建盞(けんさん)の一種で、紺黒の地に柿色の細い線条が、あるいは柿色の地に細い黒線が、口辺から内外にかけて禾目状に無数に流下しているものをいいます。
中国ではこの禾目の釉紋を兎毛に見立てて、兎毫盞(とごうさん)と呼んでいますが、これも曜変や油滴と同じように火の加減で生じたものです。なにも釉紋のない普通の建盞を、只天目といっていますが、これに次いで多いのはこの禾目天目です。釉面に禾目の出るのは、建盞だけの特色です。